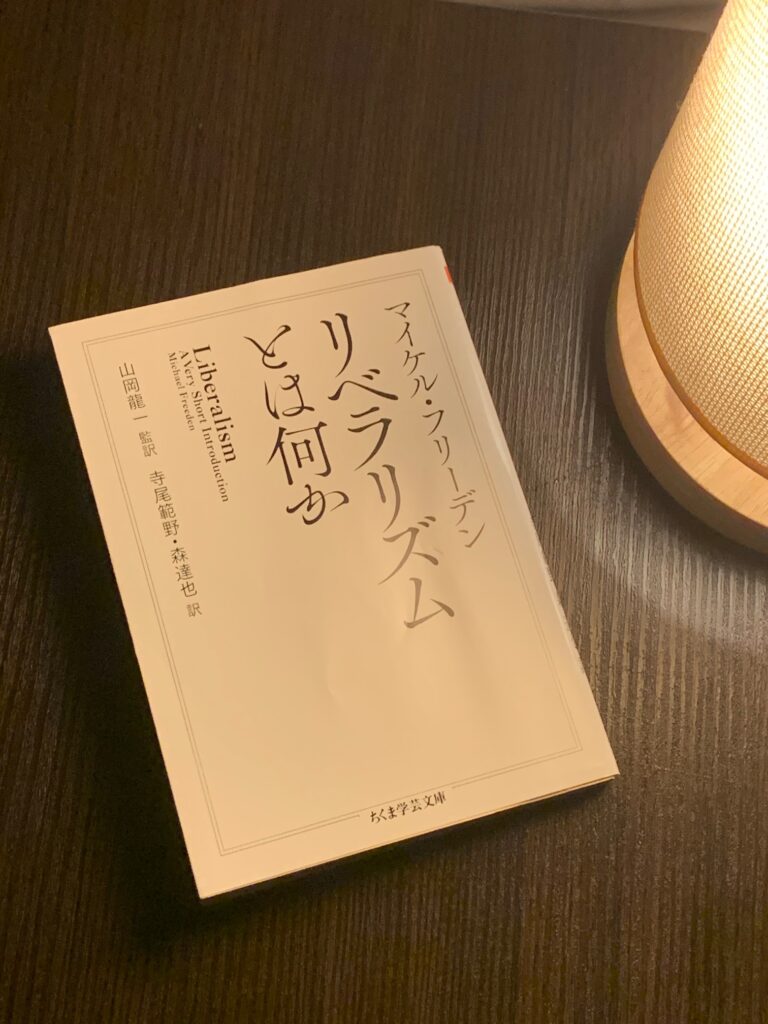
書 名:『リベラリズムとは何か』
著 者:マイケル・フリーデン
山岡龍一(監訳)寺野範野・森達也(訳)
出版社:ちくま学芸文庫
出版年:2025年
リベラルを自任する人や、リベラリズムを学ぶ人は、リベラリズムが統一された思想であって、そのさまざまな要素は時間とともになめらかに発展してきたとみなす傾向がある。[…]だが、リベラリズムのたどってきた道は、けっしてそのようなものではない。[…]むしろリベラリズムは突発的で激しい変化をこれまで経験してきたのであり、その結果として、核となる教義が収斂と分離を繰り返してきたのである(p.70)。
2025年上半期に日本でも話題となった映画『教皇選挙』。その映画の終盤、ひとつの事件が起こる。システィナ礼拝堂に集う枢機卿たちによって行われる教皇選挙が佳境を迎える中、何と礼拝堂近郊の広場で、何者かによる自爆テロが起こったのである。テロの衝撃で選挙は一時中断、騒然とする枢機卿の中、一人のイタリア人枢機卿が立ち上がり、激しい口調でまくし立てる。「これぞ、リベラリズムの兄弟たちがこよなく愛する教義の結果だ」と。
リベラル/リベラリズム…。この言葉にどのようなイメージを持っているだろうか。
自由や寛容、多様性を標榜するリベラリズムは、ひと昔前まで、どこか進歩的で自由なイメージを帯びていた。ところが現在はどうか。自国第一主義の言説が台頭し、移民受け入れに反対する政党が議席を伸ばし、人種やジェンダー問題が顕在化する現代社会において、リベラリズムは、どこか楽観的でどこか自己欺瞞的なイメージがつきまとう。さらに、格差社会を増長するネオリベラリズムの台頭によって、ますます、リベラリズムへの否定的なイメージが強まり、先の枢機卿のように激しく批判される。そう、リベラリズムは危機に瀕しているのだ。
とはいえ、そもそもリベラリズムとは何だろうか。リベラリズムとは、いつどこで生まれ、どのような思想形態なのだろうか?
本書は、近年何かと批判にさらされがちなリベラリズムという思想を、改めて歴史的に遡ってその実態に迫るというものである。考察対象は、「リベラル」という言葉が政治の舞台に登場した1810年代から現代までの実に200年。考察地域もイギリスを中心に、ドイツ、フランス、イタリア、そしてアメリカと実に多岐にわたる。
著者のマイケル・フリーデンは、1944年にロンドンで生まれたドイツ系ユダヤ人。ニューリベラリズム研究にて博士号を取得した後、ハイファ大学やオクスフォード大学にて教授職を歴任。政治哲学が現実世界に与える影響を主たる考察対象に、政治思想の内容分析に取り組む政治哲学者である。
本書においてフリーデンが試みるのは「形態学的アプローチ[morphological approach]」と呼ばれる彼独自の分析手法である(第4章にて詳述)。すなわち、リベラリズムという思想体系を構成する諸要素を特定し、それらの位置関係(諸要素がどう重なり合っているのか、あるいは重なり合っていないのか)を明らかにするというものである。こうした分析手法により、リベラリズムの内実が構造的に理解される。
興味深いのが、リベラリズムは以下の5つの相反する思想の複合体であるという点だ。
- 解放と制限を同時に唱える立憲主義的なリベラリズム
- 個人の自由を第一義とするリベラリズム
- 人間の成長や自律を促進するためのリベラリズム
- 相互の助け合いを重視し、社会全体で幸福な暮らしを目指すリベラリズム
- ジェンダーやエスニシティといった人間の多様性を重視し、マイノリティの保護を優先するリベラリズム
フリーデンによると、リベラリズムは、この5つの異なる歴史的地層の結合体であり、それらが、時代や地域によって消失と堆積を繰り返しているという。すなわち、この思想の多層性こそが、リベラリズムの特徴であり、我々のリベラリズム理解を難しくしているのである。
本書は、元々オックスフォード大学のVery Short Introductions (VSI) シリーズ(難解なテーマを分かりやすく解説する入門書シリーズ)として出版されたものである。それゆえ、全体を通じて、専門的な用語は控えめで、簡潔な文章で書かれている。
果たして、リベラリズムはもはや時代遅れの思想なのだろうか。本書は、リベラリズムの構造を理解し、現代社会のリベラリズム批判を考える出発点となる一冊である。
